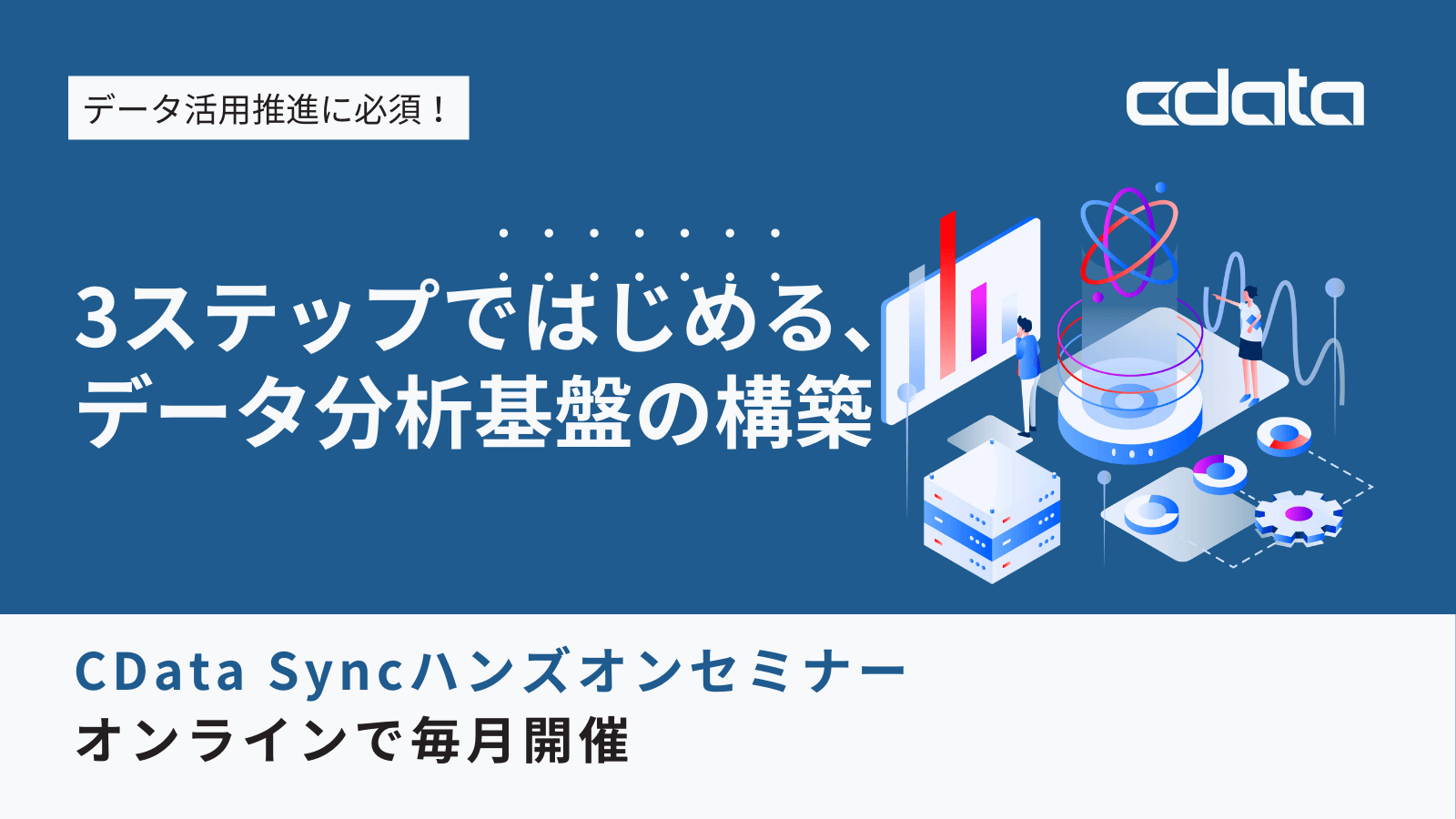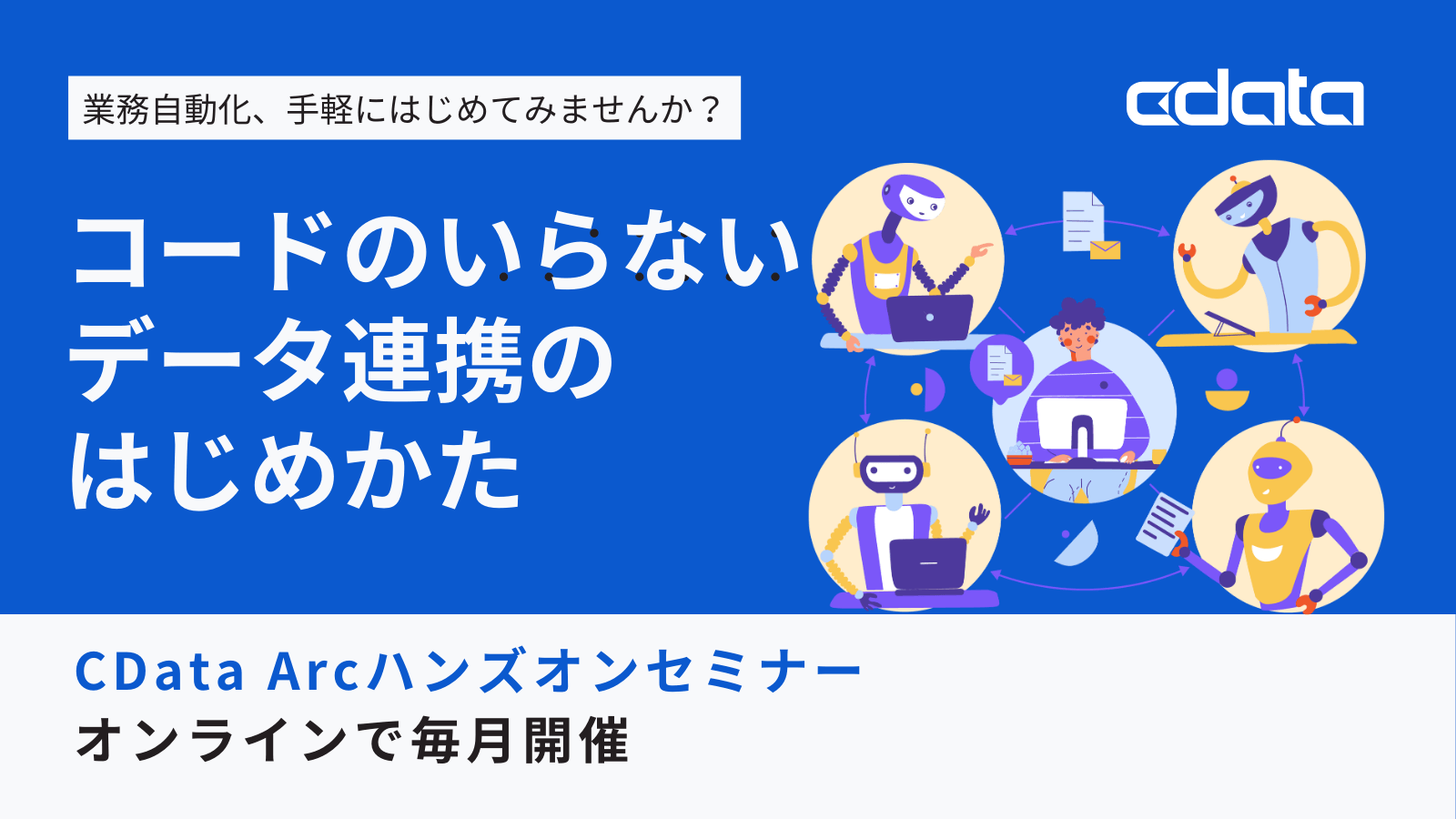ノーコードでクラウド上のデータとの連携を実現。
詳細はこちら →CData Virtuality - 無償トライアル、および、初期設定方法 (SaaS版)
CData Virtualityは、エンタープライズグレードのデータ仮想化プラットフォームです。データ仮想化によるリアルタイムデータアクセスとデータレプリケーションのバイモーダルによるデータ連携を提供します。本記事では、CData Virtualityのフルマネージドクラウド(SaaS)版の無償トライアル、および、初期設定方法についてご紹介します。
CData Virtuality - 製品のインストール、および、初期設定方法 (Windows版)
CData Virtualityは、エンタープライズグレードのデータ仮想化プラットフォームです。データ仮想化によるリアルタイムデータアクセスとデータレプリケーションのバイモーダルによるデータ連携を提供します。本記事では、CData Virtualityインストール(Windows)版についての製品のインストール、および、初期設定方法についてご紹介します。
CData Snowflake Drivers で時刻データを取り扱う際の注意点
本記事ではCData Snowflake Drivers で、時刻データを取り扱う際の注意点についてご説明します。
HCL Domino REST API の使い方:③REST API をPostman で触ってみる
こんにちは。CData Software Japan リードエンジニアの杉本です。 前回、前々回とDomino REST APIの環境構築について触れてきました。 そして、今回は実際にHCL Domino REST API を触っていきたいと思います。 API を試すときはAPI Reference の画面やcurl なども使えますが、今回はPostman を利用しました。
AWS Summit Japan 2024 レポート:ブース企画「どんなデータを分析利用したいですか?」アンケート結果を大発表!
今回CData ブースにお越しいただいた皆さんに「どんなデータを利用したいか」ヒアリングを行いました。 緑色のシールはお客様に提供するベンダーの立場、赤色のシールはデータを利用するユーザーの立場からの回答になっています。
CData Arc で、SAP Ariba のData Import/Export タスクをリクエストする
この記事ではSAP Ariba のIntegration Toolkit に含まれていたデータ転送ツール(data transfer tool)に類似の連携アプローチとして「CData Arc で、SAP Ariba のData Import/Export タスクをリクエストする」シナリオを試してみます。